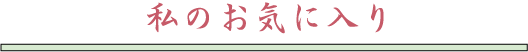
「衣・食・住」日々の生活の中で、私の好きなもの事をご紹介しています。
時には身勝手な自慢話、時には耳より情報、時にはつまらぬウンチク話・・・
ご感想、ご意見など、お寄せ下されば嬉しく存じます。
◆ 吉井さんの《玄釉鍋》 2004年 11月
九月のこのコーナーで《中川一志朗さんの炊飯土鍋》をご紹介した折に、「昔から土鍋が大好きで(コレクションとまでは言えませんが) 大小様々、いくつかの土鍋を持っています。」と、書いたところ・・・ 「他には、どんな土鍋をお持ちですか?」「他に気に入っている土鍋はありますか?」などの質問を受けました。
こと“御飯”に関しては、先述のとおり《一志朗さんの土鍋》が最高!ですが、難点は『重さ』です。母などは、「私には、持てない!」と、頭から拒否する始末です。そこで、私が持つ中で最も軽いのが《吉井史郎さんの玄釉鍋(くろなべ)》です。

田園調布・土楽の浅見さんご推薦の土鍋です。写真の向かって左、深い方の土鍋は炊き込みご飯やシチュー、煮物に最適です。右側の浅い土鍋はとにかく万能鍋ですね。いわゆる鍋物、鯛めし、鮎ごはんなど長い物、大きな物の炊き込みご飯やパエリア、煮魚や煮込み料理、さらに、炒め物からすき焼きまで・・・
《吉井さんの土鍋》は、「これ、土鍋?」と思うほどに、とにかく軽い!です。 非力な母も、片手でも楽々と持てるほどです。・・・ということで、深い方の土鍋は実家の母のもとへ嫁いで行き、毎日、大活躍しています。お手入れも楽ですね。水に浸けて亀の子でサッとこすれば、汚れはスーッと落ちます。
 それから、我が家に欠かせないのが《土楽さんの黒鍋》です。私は《ステーキ鍋》と呼ぶこともありますが、焼くことを得意とする土鍋だそうです。《吉井さんの土鍋》が来るまでは、鯛めしも鮎ごはんもこれで炊いていました。ただ、少々“浅め”なので量を多く炊くことが出来ませんでした。その“浅め”が功を奏し重宝するのが、鱧すきと牡蠣の土手鍋。我が家に欠かせない所以です。
それから、我が家に欠かせないのが《土楽さんの黒鍋》です。私は《ステーキ鍋》と呼ぶこともありますが、焼くことを得意とする土鍋だそうです。《吉井さんの土鍋》が来るまでは、鯛めしも鮎ごはんもこれで炊いていました。ただ、少々“浅め”なので量を多く炊くことが出来ませんでした。その“浅め”が功を奏し重宝するのが、鱧すきと牡蠣の土手鍋。我が家に欠かせない所以です。
《土楽さんの土鍋》は、保温性が抜群!です。実は、教室で使う為に、「この土鍋をもう一つ買い足したい」と、田園調布の土楽さんを訪ね、先の《吉井さんの土鍋》を教えていただきました。やはり、お店に足を運ばないといけませんね。。。
他にも数点・・・ それぞれ、どの土鍋に一長一短ありますが、上手に使い分けています。土鍋をお求めの際は、用途と収納を充分に考慮して頂きたいと思います。私も、デザインに惚れて・・・収納に泣いたこともあります。