
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や12年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2008年 1月 御菱葩と花びら餅
今やお正月には欠かせないお菓子となっている「花びら餅」ですが、明治のはじめ、裏千家11代家元玄々斎が川端道喜さんに初釜用の「御菱葩」(おんひしはなびら)の創作を依頼し、12代の道喜さんが現在の製法にて作り出されたもの が最初とされています。 今日 みる「花びら餅」はそれが、お正月のお菓子として全国に広まり、各地の和菓子屋さんで其々の「花びら餅」が作られるようにな ったものです。
「御菱葩」は、宮中の正月行事である『歯固めの祝』に用いられる鏡餅を基に作られたもので、道喜さんに残る文献(宮中の行事御用品を表した絵巻物)には、三宝の上に円形の白い餅に紅色の菱形の餅を交互に12枚重ね、その上に搗栗や榧の実、押し味噌、2匹の干し鮎などが並べられた絵図が残されているそうです。 江戸時代の初期に鮎が牛蒡に変わり、味噌がぬられた「御菱葩」の原形が宮中正月宴に初献され、その後、代々の天皇が正月恩賜の配り物としてお使いになり「宮中雑煮」とも呼ばれていたものだそうです。
利休大居士以来、禁中献茶を念願していた11代家元玄々斎は、慶応元年の八朔と慶応2年の正月にその望みが叶い、これ以降、恒例献茶となった喜びを一門にわかつため、御所より持ち帰った先述の正月恩賜の「御菱葩」を砕いて饅頭の原料に混ぜ初釜用の主菓子としてお祝いしたと言われています。 東京遷都の後、許しを得て裏千家初釜用の「御菱葩」 の創作を依頼したのが「花びら餅」の起源です。
 現在、裏千家の初釜式で出される「御菱葩」は牛蒡が手前です。 平成17年の初釜式からお菓子の向きが180度変わりました。 平成14年の12月に現、坐忘斎御家元が襲名されて3度目の初釜のことでした。 私は目の前に運び出された「御菱葩」の向きに驚いてお運び下さった先生が向きを間違えられたのだと思い、いつ逆さまに変えようかしら… と、ドキドキしました。 ふと周りを見るとどのお菓子も逆さま向きで… 訳が分からぬままに帰宅し、先に初釜に参加した友人に確かめました。。。 「今年(2005年)から変わったのよ。 先生が道喜さんにお電話したら、『お使いになる方のご自由です』と仰ったそうよ」
御家元のお好みにより、お菓子の向きは180度回転したのです。 私はその年、既に牛蒡を向こうにして自宅の初釜を行った後でした。 また東京の初釜では、席中がどよめいたと聞いています。(笑)
現在、裏千家の初釜式で出される「御菱葩」は牛蒡が手前です。 平成17年の初釜式からお菓子の向きが180度変わりました。 平成14年の12月に現、坐忘斎御家元が襲名されて3度目の初釜のことでした。 私は目の前に運び出された「御菱葩」の向きに驚いてお運び下さった先生が向きを間違えられたのだと思い、いつ逆さまに変えようかしら… と、ドキドキしました。 ふと周りを見るとどのお菓子も逆さま向きで… 訳が分からぬままに帰宅し、先に初釜に参加した友人に確かめました。。。 「今年(2005年)から変わったのよ。 先生が道喜さんにお電話したら、『お使いになる方のご自由です』と仰ったそうよ」
御家元のお好みにより、お菓子の向きは180度回転したのです。 私はその年、既に牛蒡を向こうにして自宅の初釜を行った後でした。 また東京の初釜では、席中がどよめいたと聞いています。(笑)
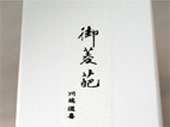 また、昨年(2007年)の初釜式からは、牛蒡が完全に餅の中に隠れています。 道喜さんの味噌餡は流れるほどに柔らかいため、
毎年お着物を汚される方がかなり多く、これに配慮してのことと説明がありました。
また、昨年(2007年)の初釜式からは、牛蒡が完全に餅の中に隠れています。 道喜さんの味噌餡は流れるほどに柔らかいため、
毎年お着物を汚される方がかなり多く、これに配慮してのことと説明がありました。
従来二つ折れのお菓子は山が向こう、口を手前に用います。 裏千家門下である私は初釜にのみ牛蒡を手前で扱いますが、和菓子のお教室や一般のお客さまには牛蒡を向こうにお出ししています。 牛蒡も道喜さんは宮中の鮎にならって細いものが2本ですが、一般には1本が多いようです。 さらに地方に行くとお雑煮を模していることから人参の入ったものもあるようです。 (笑)
もちろん私も「花びら餅」を作りますが、出来上がった「花びら餅」を眺め、白いお餅の下から薄っすらと紅色が透けて見え、ふっくらとした何とも愛らしい姿に笑みがこぼれます。 各お店によって様々な意匠があり、とても興味深いお菓子でもあります。
昨年のお正月、道喜さんの奥様とお話させていただく機会に恵まれましたが、その折にも「御菱葩」の向きに触れ、私が「海外向けのご本の中に「御菱葩」が縦になって紹介されている写真がございましたね?」とお話したら、「あの方は面白いカメラマンでした。。。 うちのおばあちゃんが言った通り、お食べになる方の自由ですから…こちらが言うことではありません」とのお返事が戻ってきました。 室町から続く禁裏御用を誇りとする名店は懐が深い!と、感心した次第です。